「初めて大阪万博に行くけど、どう回ればいいかわからない…」そんな方のために、5日間で43のパビリオンを見学した私の体験をもとに、万博の歩き方をお伝えします。
2025年5月21日から25日までの5日間、お昼は会場でボランティア活動、夜は夜間チケットで観覧。実際に体験したことやボランティア仲間から聞いたリアルな声も交えて、「初めてでも迷わず楽しめる万博攻略法」を紹介していきます。
万博を楽しみつくすための鉄則
鉄則①:並ばないためには「予約」が命!
万博会場はとにかく「人、ヒト、ひと」。
人気パビリオンはどこも長蛇の列で、「見学」よりも「行列」がメインになりかねません。
だからこそ、並ばずに入れる“事前予約”は絶対に活用すべきです。
🔹 失敗談:予約を軽視した私の反省
私は、2か月前抽選が面倒でスルーしてしまい、これが大失敗でした。
結果、7日前抽選では5日間で1つしか当選せず、空き枠の先着予約もすべて敗退。
パビリオンに並び続ける日々となりました…。
🔹 予約システムは4段階ある
1.2か月前抽選
来場日時予約をした日の3か月前から2か月前の前日まで受け付ける、パビリオンやイベント観覧の抽選申し込み
2.7日前抽選
来場日時予約をした日の1か月前から8日前まで受け付ける、パビリオンやイベント観覧の抽選申し込み
3.空き枠先着
来場日時予約をした日の3日前から前日の午前9時まで受け付ける、パビリオンやイベント観覧の先着予約申し込み
4.当日登録
会場に入場して10分後から受け付ける、パビリオンやイベント観覧の予約

当日登録は、スマホでできますが、5月時点では反応が遅く、枠が埋まっても反映されていないことが多いので、当日端末を使用して登録するほうがいいと言われています。できれば、青印のクエート館前の当日登録センターが16台端末あるし、アテンダントもいるので、個々を利用するのがいいらしいです。私も4日間登録できなかったので、5日目にここに並びました。並んでいる間にスマホで登録を試みたら奇跡的に取れたので、それ以上ならばなくて済みましたが、大勢の人がここも並んでいます。
鉄則②:比較的空いている「ゴールデンタイム」を狙え!
大阪万博の営業時間は公式には22時までですが、実際はパビリオンの受付終了が20:30ごろのところが多く、実質的な行列の締め切りはもっと早めです。
🔹 例:アメリカ館は19:30前後に受付終了していました。
🔹 狙い目の時間帯は「朝一」と「夜後半」
多くの修学旅行団体や子連れの家族連れは、夕方までに会場を後にするため、夜間の遅い時間帯(19:30〜20:30)は比較的空いてくる傾向があります。
また、朝の9:00〜10:00ごろも比較的空いているとの情報が現地ボランティアの間でも共有されていました。
🔹 ただし、夜は“見どころ”とのトレードオフ
夜の19:30ごろからは、屋外でのプロジェクションマッピングや噴水ショーが始まり、さらに20:57からは約10分間のドローンショーも行われます。
そのため、パビリオンを優先するか、夜の演出を楽しむか、計画段階で決めておくことが大切です。
🔹 結論:ゴールデンタイムにパビリオン見学を集中すべし
- 朝イチ(9:00〜10:00)
→ 開場直後は人が少なく、人気パビリオンも並びやすい - 夜後半(19:30〜20:30)
→ 人が減ってくるが、屋外ショーとの時間が重なる点に注意
見学と演出、どちらを優先するかを決めたうえで、空いている時間帯を最大限に活用しましょう。
鉄則③:並ばずに“建築と空中散歩”を楽しめ!
万博といえばパビリオンの展示を観るのが王道ですが、実は“並ばなくても楽しめる要素”もたくさんあるのをご存知ですか?
🔹 パビリオン建築そのものを楽しむ
各国のパビリオンは、世界の一流建築家たちが手がけた個性豊かな建築物。
展示に入らなくても、外観を眺めているだけでも見応えがあります。
特に夜になると、ライトアップで幻想的な雰囲気に包まれ、まるで建築美術館のような景色に。
パビリオン間の移動中も、ぜひ外観やデザインのディテールに目を向けてみてください。
🔹 万博の全景を俯瞰する「大屋根リング」
そしてもう一つのおすすめが、**万博会場のシンボル「大屋根リング」**です。
- 会場の中心をぐるりと囲む、全長約2kmの屋上デッキ
- 上から会場全体と大阪の街並みを一望できる絶景スポット
- 登ると、スマホの地図と照らし合わせて位置関係を直感的に把握できるので、
→ その後パビリオンを回る際の“方向感覚”が明確になってとても便利です - 音楽が流れており、まるで空中の遊歩道のような空間
🌙 夜はライトアップされ、幻想的な散歩コースとしてもおすすめ。
⏰ 入場は21:00まで。歩いて一周すると30〜60分ほどかかります。
どこからでも自由に上り下りできるので、スケジュールに合わせて気軽に立ち寄ってみてください。
“並ばずに楽しめる”視点を持つことで、万博の魅力がさらに広がります。
お昼過ぎ、混雑がピークの時には、こういう散歩がおすすめですよ。
鉄則④:迷ったら「コモンズ館」に行け!
万博に来たなら、できるだけ多くの国の文化に触れたい――でも、並んでいて時間が足りない…。
そんなときは、迷わず「COMONS(コモンズ)館」へ向かいましょう。
🔹 89ヵ国が一気に集まる“裏メイン会場”
- COMONS館はA〜Fまで6棟ありますが、A〜D館に89ヵ国が集結しており、158の参加国の半分以上がここに集中しています。
- 展示ブースには各国の紹介映像や文化的展示品があり、まるでミニ海外旅行。
- トイレもあり、休憩にも最適。混雑も少なく、並ばずに入れるのが最大の魅力。
🔹 展示だけじゃない“生の交流”も
- スタッフがその国の出身者であることも多く、話しかけるとリアルな話が聞ける。
- 物産品やスイーツの販売、各国のスタンプ収集なども楽しめて、効率よく“万博感”を味わえる場所です。
🔹 一つでも訪問すれば“万博に来た感”は充分
すべて回る必要はありません。
A〜Dのうちどれか一つだけでも訪れてみてください。
「たくさんの国に触れた」「異文化に触れた」という体験は、確実に印象に残るはずです。
🔹 ナセルの体験から:コモンズ館は「人生のきっかけ」になる場所かもしれない
私は、小学生のときに初めて万博に行きました。
そのときに目の前に広がる、たくさんの外国人たちの姿に衝撃を受けたのを今でも覚えています。
「世界はなんて広いんだ」「いつか海外で働いてみたい」――
そんな気持ちが芽生え、結果的に私は16年にわたって海外で暮らす人生を選ぶことになりました。
だからこそ、お子さん連れの方には、ぜひコモンズ館に足を運んでほしいと思います。
国の数だけ世界があり、そこに実際に“人”がいるという体験は、子どもにとってかけがえのない記憶になるかもしれません。
鉄則⑤:雨具を持っていけ!〜万博は“全天候型アウトドア”だ〜
人気パビリオンには、どうしても並ぶ必要があります。
そして、その待機列の多くは屋外です。
天候が不安定な春〜夏の時期に、一日中屋外にいるということは、**「雨」「炎天下」「風」「寒さ」**のすべてに備える必要があるということ。
🔹 傘とレインコートは必携アイテム
- **傘は日傘兼用タイプがおすすめ。**日中の直射日光を避けるだけでも疲労感が全然違います。
- **レインコートは強風時にも有効。**会場は海沿いにあり、風が強いため、雨が横から吹き付けてくることも。傘だけでは対応しきれません。
- 夜間は気温が下がることもあるため、防寒具代わりにもなるのがレインコートの良いところです。
🔹 屋外待機に便利な“アウトドアグッズ”も活躍
- 小さく折りたためるアウトドア用の椅子を持参して、列に並びながら座っている人も多く見かけました。
- 大屋根リングにはベンチもありますが、基本的に混雑していて空いていません。
- そんなときはレジャーシートを敷いて休憩している人たちもいました。自分のスペースを確保するのにとても便利です。
🔹 万博=全天候型アウトドア体験と思え
万博は“屋内イベント”というよりも、アウトドアアクティビティだと考えて準備をすると快適度がまるで違います。
✅ 雨具・日傘・レインコート
✅ 折りたたみ椅子 or レジャーシート
✅ 夜間用の軽い羽織もの
快適な装備=心の余裕。天候に振り回されず、思いっきり楽しむための準備として、雨具は鉄則です。
🟦 未来を見せてくれた1970年、問いかけてきた2025年
私は小学生のとき、1970年の大阪万博に行きました。
月の石、テレビ電話、動く歩道――どれも本当に驚きで、「未来ってこうなるんだ」と、子どもながらに確信したのを覚えています。
そしてその未来は、数十年後に現実になりました。
だから、2025年の万博にも、どこかで同じような期待を持っていたのかもしれません。
まだ見ぬ技術、本物の未来。そういうものを“見せてくれる”と、どこかで思っていたのです。
けれど、今回の万博は違っていました。
海外のパビリオンの多くは、ほぼすべてが映像中心。
展示品はなく、プロジェクションやイマーシブな演出で未来のテーマを表現していました。
企業パビリオンも、AIによる自動化など「予想できる未来」が多く、「これ見たことない!」という衝撃は正直少なかった。
一瞬、「あれ? これってYouTubeで見られる内容とあまり変わらないのでは?」と思ったほどです。
でも、そういう違和感を抱きながらも、何日も歩いて、いくつものパビリオンを回るうちに、ふと気づきました。
今回の万博は、“未来を見せてくれる場”ではなく、“未来について問われる場”だったのではないか、と。
実際、多くのパビリオンで私は問いかけられました。
「あなたはどんな未来を望みますか?」
「何が必要だと思いますか?」
「何を大切にしたいですか?」
そしてその声を録音し、AIがそれをもとに未来像を生成するような試みもありました。
それは、1970年のように“未来はこうです”と提示される万博とは、明らかに違うアプローチでした。
コモンズ館を見ていて、「こういう国で暮らしたらどうなるだろう」と想像したとき、自然の生活のことを思いおこしました。
いろんな国のミニチュアを見て、自分の生活をあらためて見つめ直していたのです。
「自分はどこに、どう暮らしたいのか」――
未来社会のデザインを考えるというのは、結局、自分自身の未来のあり方を考えることなのだと思いました。
1970年の万博は、未来を見せてくれた。
2025年の万博は、未来について考える時間を与えてくれた。
驚きは少なかったかもしれません。けれど、“自分の未来”を見つめ直すという意味では、深く心に残る体験でした。
そして私は、やっぱりこう思うのです。
今回の万博にも、来てよかった。


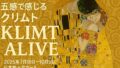

コメント